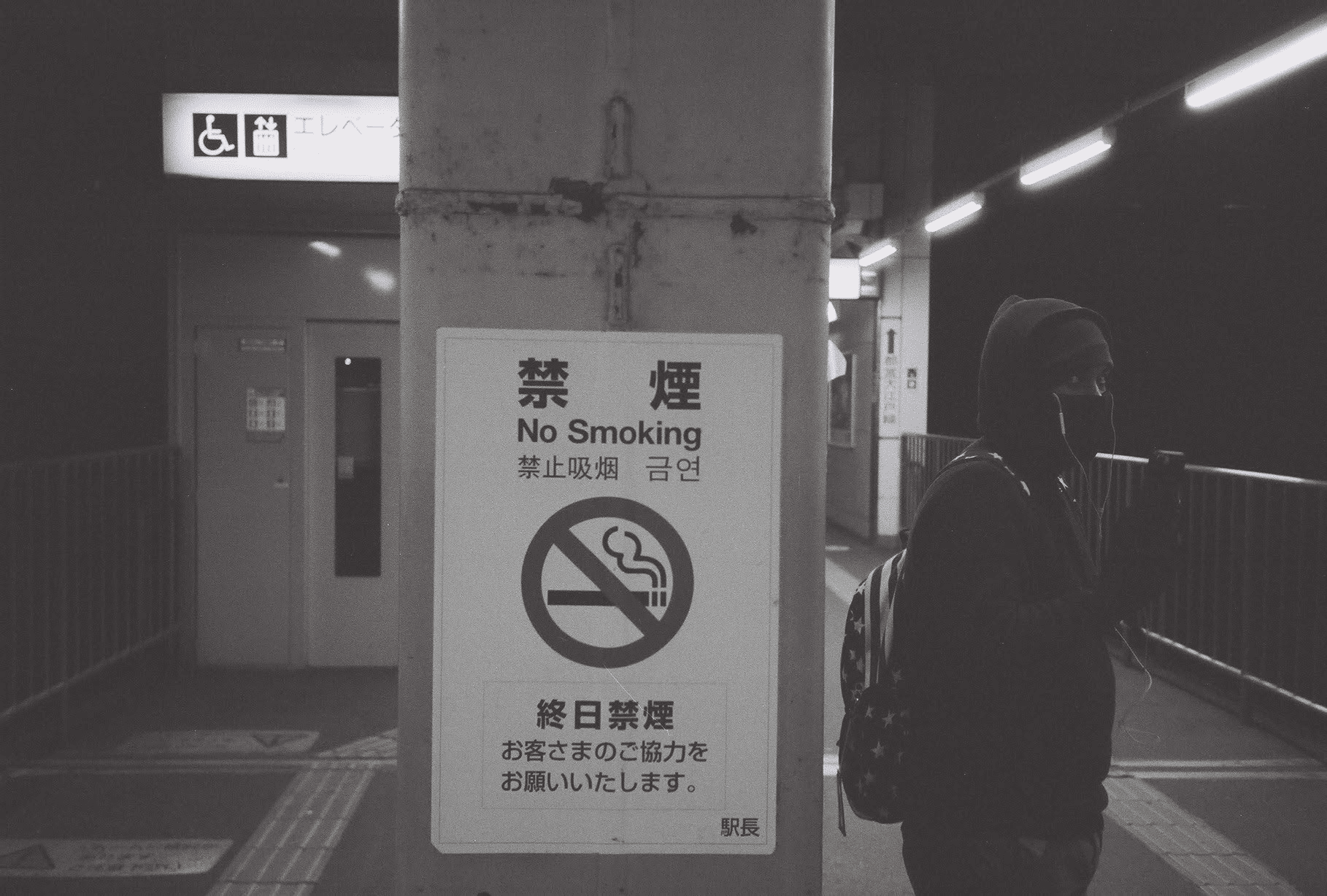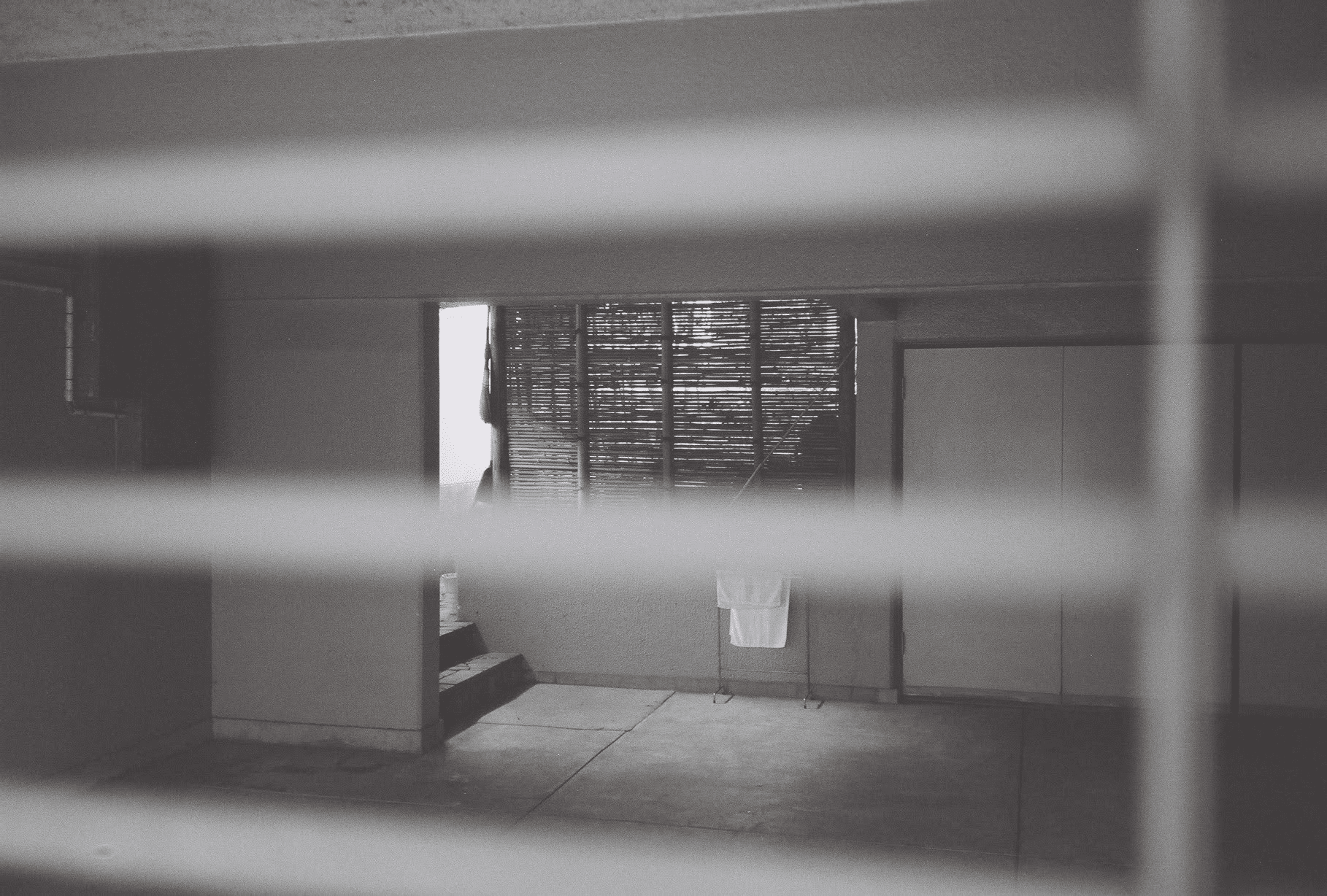全然予定はなかったのですが、急に昼ぐらいに出発して成田へ。浜松でうなぎを食べなかった話を前の日にしてて、なんか食べたくなったんですよ。そういうわけで成田山の表参道。前に来たときは高校生だったので、十数年ぶり。前に来たときはめちゃのどかに歩けたような記憶があったんだけど、Go Toしに来ている人たちが多いのか、連休前というのになかなかの人出。おまけに車も普通に参道を通るので、歩きにくいなあなんて思いながら。でも街並みは変わらず美しい。





有名店らしい川豊さんで上うな重。これが食べたかった。満足度高し。ほかのお店との違いはわかりませんが目的は果たせた。お店の建物が有形文化財らしいのですが、登録が令和2年4月となっており、意外と最近だった。






新勝寺といえば、節分の日に力士が豆まきに来るんだけど、だいたいその時の第一人者、つまり現在なら横綱白鵬がほぼ必ず来ているはずです。何か規定みたいなものがあるのだろうか…









夜はMUSIC GATEの配信ライブを見ないといけなかったので、一通り回ってそそーっと帰ったのでした。滞在2時間で楽しめる小々旅行。