16年間で初めて一つも記事を書かない月になりそうだったので、久しぶりに1年の個人的によく聴いた音楽の話をします。5年ぶりぐらい?いつのまにか2010年代は終わってしまいました。去年2018年の分もだいたい書いたんだけどなぜか日の目を見ていないので、そのうち上げるかも。
Tatiana Nikolayeva / Shostakovich: 24 Preludes and Fugues, Op.87 (Melodiya&Venezia, 1987)

しばらく続いていたバッハ・アレルギーを克服したタイミングで、このショスタコーヴィチの大作を聴いてみようと思った。初演者であるニコラーエワによる2つめの録音。バッハの形式を借りてはいるが、深遠な精神性を纏った現代的な旋律が、幾度も顔を変えながら続いていく。絶対音楽としての精緻な構造美の内に、作曲者が隠した複雑な心の機微をたしかに読み取ることができる。ニコラーエワのタッチは、必要以上の情感を廃した厳然さを保ちつつ、鳴っているピアノを今ここで聴いているような、開かれた親しみやすさと近さも併せ持つ。彼女のピアノを案内役として、あたかもパズルを解くように、築かれた迷宮の扉を順に開けていくように、淡々と記憶を紐解いていく静かで心地よい営み。小さな部屋でただひたすらに聴いていたい。
Danish String Quartet / Prism II (ECM New Series, 2019)
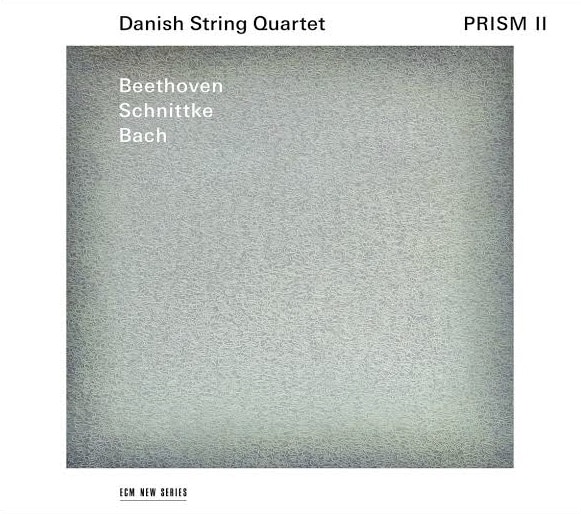
デンマーク弦楽四重奏団の作品集。とりわけ、シュニトケ「弦楽四重奏曲 第3番」をよく聴いていた。アルフレート・シュニトケという作曲家は劇的なまでに不安定で、同じ楽曲、同じ楽章の中でも目まぐるしくアメーバのようにその曲調を変えていくものだから、「そこでキレる!?」みたいなことがままある。激情の嵐と濁流、そのあわいに凪を垣間見て、すぐまた深い絶望の荒波に飲まれていく。自分が不安定なときに聴くと、急激な波と自分とが共振して、うねりを伴う不思議な感覚に陥ってしまう。一見して混沌な面もあるが、様式も技法も表現のための道具にすぎないという点は、他の20世紀音楽にない明快さだと思う。
バッハとベートーヴェンにシュニトケがサンドされるというこのアルバムの構成は、前作Prism Iを踏襲している。ただし前作で挟まっていたのは、やはりひたすらに不安定なショスタコーヴィチ「弦楽四重奏曲 第15番」だった。このカルテットがアルバムの中で浮かび上がらせようとしたものが見えてきて面白い。
Fumio Yasuda / Forest(Winter & Winter, 2019)

上からの流れで、自分の中で室内楽的な響きを求めていたところがあって、ジャズを聴くにしてもそういう方向に引っ張られていたのでした。ピアノとベースが空間をつくり、ヴォーカルにリード(クラリネット)が絡む、個人的に好きな組み合わせ。Winter & Winterというレーベルの作品は長いこと聴いているけれど、レーベルの看板アーティストの一人である安田芙充央の作品は意外と通過していなかった。優れたコンポジションもさることながら、 具象と抽象を織り交ぜながら深い森の情景を描き出す独特の語法のピアノが心地いい 。Akimuseによるヴォーカルは何語でもない言葉で歌われているようで、ピアノとともに音楽全体の浮遊感を演出している。むしろ、その浮遊感に任せて漂うヨアヒム・バーデンホルストのクラリネットのほうが「歌」なのかもしれない。演奏がフリーキーな方向へ振れる場面もあるが、受ける温度感は一定して低く、霧の中で揺らめく冷たい炎を想起させる。そして、「室内楽的」とは書いたものの、研ぎ澄まされた緊張感をもってこの音楽の語り口を最終的にジャズたらしめているのは、井野信義のベースによって、だろう。同居する浮遊と緊張のバランスに、ステファン・ウィンターのサウンドプロデュースの妙を見る。
バーデンホルストは色々な作品に顔を出していて、プリペアドピアノを含むトリオ、Watussiも素晴らしい。安田の過去の作品も聴いてみたくなった。