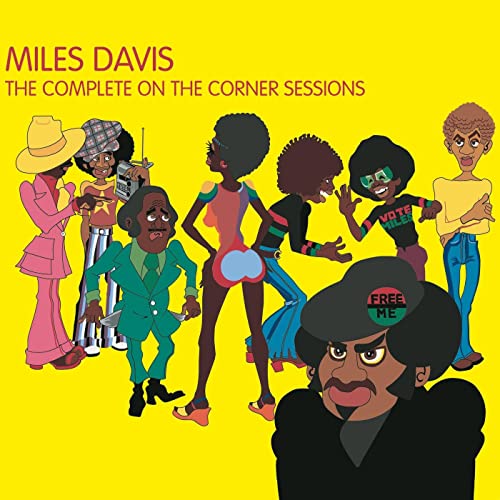久しぶりに、というか毎回久しぶりなT-SQUAREのライブ。安藤正容さんの歓送ライブということで、センバシックス、THE SQUARE Reunion、T-SQUAREの3部構成の対バンみたいなイベントです。
センバシックス
センバシックスの演奏は元T-SQUAREメンバー2人を含む編成。センバシックスというのはレギュラーで活動しているのかと思ったらこの日のためのバンドだったらしいです。ヴァイオリンが入っているのがユニークで、楽曲もオリエンタルな雰囲気があって、エレメントとしてはマハヴィシュヌみたいな趣。リズムアレンジは仙波さんにしてはシンプルに乗れるファンク風味でしたが、ヴァイオリンとギターが織りなすメロディがなんとも言えず奇怪でクセになります。是方さんのジミヘン的な(というよりピート・コージー的と言ったらいいのか)ファジーにドライブするギターは良い感じにフュージョンっぽさが抜けていてかっこいいなあと。ふと周りを見れば、濱田遼太朗さんの師匠直伝の不思議なパーカッションや、フレットレスベース、やけにメロウなエレピなどなど、全員が全員なかなかのカオス。全体的にT-SQUARE聴きに来た人をちっとも相手にする気がないのが面白い(笑)
THE SQUARE Reunion
そんな第1部を受けてのTHE SQUARE Reunionは和泉宏隆フィーチャー…とはいえ和泉さんはこの場にいないので、全曲が和泉さんの楽曲ということに。席の空いたピアノにスポットライトを当てたままソロピアノ「宝島」が流れたときはさすがにしんみりしてしまいましたが…そこからバンドの演奏が入ってみると、やはりその親しみやすいサウンドに自然に身体が反応します。「宝島」から「OMENS OF LOVE」まで、珠玉という言葉がふさわしい名曲ばかり。本人のピアノを聴くことはもはや叶いませんが、遺してくれたものの偉大さに改めて感じ入ります。そして、則竹さん、須藤さんの演奏を聴くのも本当に久しぶり。「宝島」から「BREEZE AND YOU」「EL MIRAGE」と来て、やはり自分は則竹裕之の16ビート、須藤満のスラップベースで育ったのだなと思わずにいられません。まさに熟練の職人芸。また、伊東さんがしきりに「安藤”様”ともこれで最後です」と言ってましたが、「TRAVELERS」のコーダ部がギターとEWIが絡み合うオリジナル通りのアレンジになっていたり、「OMENS OF LOVE」のおなじみのギターソロなど、安藤さんと伊東さんのコンビも際立つ構成にもなっていました。バンド全体と呼応しながら勢いを増していく「BREEZE AND YOU」での佐藤雄大さんのピアノソロも忘れてはいけません。大バラード「TWILIGHT IN UPPER WEST」をライブで聴いたのは個人的に14年ぶり。そのときは和泉さんのピアノでした。思い出に溢れた曲たちを濃密な演奏とともに堪能できたことがシンプルに嬉しかったですね。
T-SQUARE
続くのはTHE SQUAREよりぐっとスマートでスタイリッシュなイメージの現行T-SQUARE。先ほどまでとは違った疾走感が「FLY! FLY! FLY!」「閃光」からあって、リズム隊の違いによるコントラストがくっきりと。この15年来ずっとそうですが、坂東慧の前のめりなほどにアグレッシブな、しかし正確無比なドラムスがこのバンドのカラーを決定づけています。どの曲でも面白いほどにフィルがスコーンとハマり、演奏のテンションが際限なく高まっていく。ユニットT-SQUARE alphaになることで、この強みもさらに先鋭化していくのかなと。去年バンドを退団した河野さんが入っての「Rondo」は、そんな魅力がてんこ盛りの名曲。河野さんと坂東さんの体制になってから数えきれないほど演奏してきたこともあって、楽曲の成熟度が一段違うレベルにあります。曲中、坂東さんと河野さんが何度もアイコンタクトを重ねながら演奏していて、この15年あまりで培ってきた関係性が窺えて泣けてきてしまいましたね。「Rondo」に代表されるように、純粋なフュージョンというよりはインストゥルメンタルポップ的指向を強くする近年の流れではありますが、「閃光」では安藤さんのロングソロあり、「Growing Up!」での全員ソロありと、それぞれのセッションプレーヤーとしての面目躍如といった部分も存分に楽しめる構成。やはり自分が実際に見てきたT-SQUAREの大部分はこの人たちなので、家に帰ってきたような感覚の第3部でした。
アンコールにはドラマー3人とパーカッジョニスト1人による恒例の「オレカマ」もありました。ソロイストたちが独自の世界を押し広げて生み出したうねりが、最後のテーマで見事なまでに収斂していく様が爽快そのものです。その後は全プレイヤーが揃ってのこれまた恒例「Japanese Soul Brothers」。ピアノソロが佐藤さんのシンセと飛び入り参加の白井さんのピアノのソロ回しになっていたのは新しい流れでした。ベースソロも須藤さん・晋吾さんと渡辺さんのスタイルが違いすぎて面白かった。中盤のソロ回しは2コーラスぐらいで割とあっさりでしたが、ここでも高橋香織さんのヴァイオリンがいいアクセントになっています。河野さんが入っているのも嬉しいですしね。最後はこの分厚いアンサンブルによる「TRUTH」で大団円。
安藤さんのフェアウェルライブとは言うもの、思ったより安藤さんが前に出る場面が多いわけでもなく、特段いつものライブと変わらない感じではありました。なんならいつものライブより安藤さんの曲が少ないまである(笑)まあひかえめな安藤さんらしいというところでしょうか。安藤さん45年間本当にお疲れ様でした。
ここまで書いておいてなんですが、この日は最前列で見ていたんですよ。伊東さんのサックスの音圧を肌で感じられたり、安藤さんや須藤さんの手技が間近で見れたり、なかなかない濃い体験をさせてもらったような気がします。本当はアイドル観に行く予定の日だったんだけど()T-SQUARE alphaも早いうちに観れればいいなー。
SETLIST
センバシックス
- GIVE ME UP
- MASALA ROAD
- DO-NESHIAN
- 夜の波うちぎわ
- 花火
- 梅肉エキス
THE SQUARE Reunion
- 宝島
- BREEZE AND YOU
- TWILIGHT IN UPPER WEST
- TRAVELERS
- EL MIRAGE
- OMENS OF LOVE
T-SQUARE
- FLY! FLY! FLY!
- 閃光
- Only One Earth
- Growing Up!
- Rondo
Encore
- オレカマ
- Japanese Soul Brothers
- TRUTH